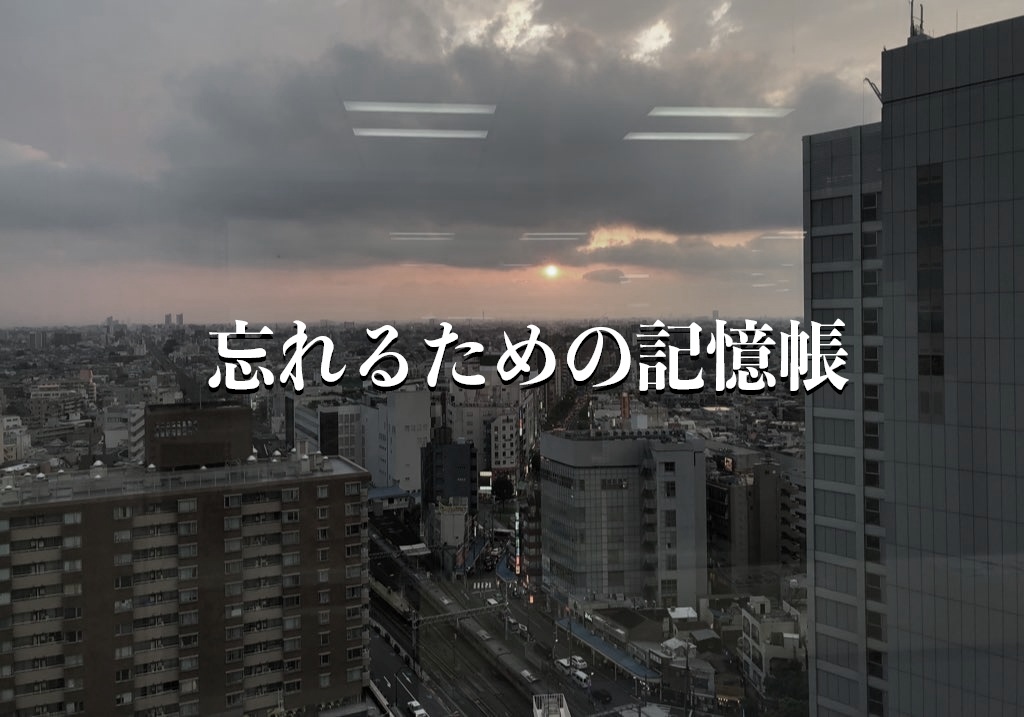また暑さが戻ってきて真夏のような装いと秋らしい装いが同居しているのを見るのは楽しいもんである。違うものが入り混じってる状態は健康的だ。気温の振幅が激しいと体調を崩しがちなものだが、歳を食うほどに気候で風邪をひいたりしなくなってる気がするのは付き合い方を覚えたということだろうか。
この2週間も粛々と仕事に勤しんでいた。もう一息で自分の手持ちの仕事は落ち着きそうなところまできている。自分の仕事で手一杯で人様の作品を見る余裕がなかなか無いのだが、また沢山のタイトルが発表されていて、その中からどの作品を見るか選ぶだけでも大変そうだななどと思ったりしている。
私の担当している作品も多数の作品の中から選ばれなければ見てもらえないのであって、それはもう半分運任せ。
逆に半分は確率を上げる方法はあるということではある。
沢山作品があるということは、見る側からしたらニッチでも自分の琴線により触れる作品に出会える可能性が高まるが、作品の鑑賞がみんなの共通体験となるような機会は低まる。これはどっちが楽しいのやら分からないが時代はずーーっと細分化へ向かい続けている。
我々が若い頃、おじさんたちは若者が共通体験を持たないのは気の毒だと言っていたが、気の毒かどうかは検討の必要があろう。
細分化と多様化は似ているようで違う。
作品の細分化のされかたに比べて多様化が進んでいるのか、全体像を印象で掴むのも難しくなっている。
なるべく多様に越したことはない、と思うが、それはほとんど見られない作品も存在することができるということなので贅沢なことである。
10年前に比べたらかなり多様になったのは間違いない。
しかし、多様性はがっちり経済の豊かさと結びついているので一瞬で消えていったりしがちである。
アニメ業界が儲かってりゃ、いろんな作品ができるという単純なことでもある。
しかし儲かってなくたって多様でありたいのだが、それにはどうしたらいいのか難しいところだ。
この間、我々より少し上の世代の仕事仲間と話していて、やはり80年台のアニメブームは凄かったのだ、と思わざるを得なかった。
なにが凄かったかといえば、作り手側の年齢と観客側の年齢が非常に近かったのだということだ。
当時は10代や20代前半で作画監督や監督をしている人たちがいて、もちろん30代以上のベテランの人もいたのだが、スタッフの平均年齢が圧倒的に若かった。
今は60〜40代前半がボリュームゾーンだと思われる。
80年代アニメが圧倒的に若者文化だったのは、作り手との距離の近さが大きかったのだと思う。
今は、基本的には歳上のスッタッフが若い人へ作品を提供するという構図だ。
これが悪いというわけではないのだが、歳の差はどんどん広がり続けるので、これをどう捉えるかは、ちと考える必要があろう。
若い人に向けたものは若い人が作った方が良いと思う。
それには若いスタッフを育てるしかないのだが、そもそも若い人が少なくなってきているのと、育てる環境が崩壊しているのが相まって、若い人が若いうちに活躍しづらい状況なのかなと思う。
それも10年くらい前に比べれば少し改善したとは思うのだが…。
膨らんでいく予算も若い人を前に立てにくくなっている一因かもしれない。
まあなんにせよ、多様性は豊かさなのである。