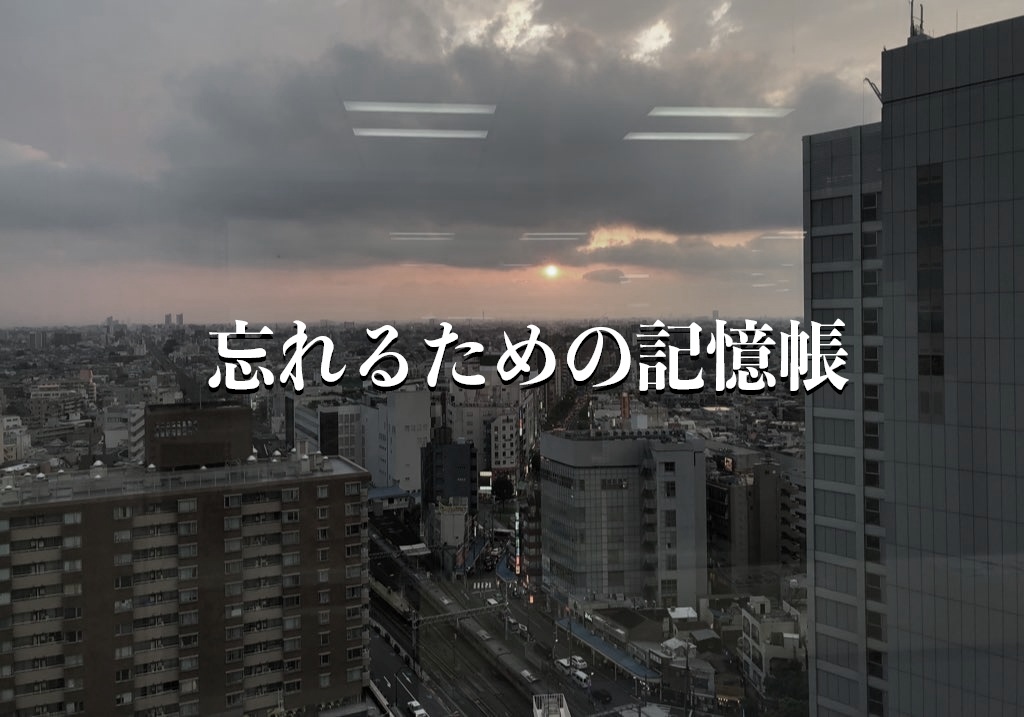相変わらず切羽詰まっていて、ブログなんか書いてないで仕事しろよと思われそうな状況が続いている。
今月を抜ければ少しはマシになるかもしれないが。
久しぶりに演出の仕事をしている。
世間というか業界人は作品数が増え過ぎて、スタッフのレベルが下がったという人が結構いるが私自身はそれほど変わりないと感じている。
私の担当は初回だしメンバーもそれなりに気を遣っているということは言えると思うが、いい感じというわけでも悪くもなく、まあこんなもんだろうなというアベレージのスタッフクオリティだ。
もちろん下を見ればキリがないだろうし上もまた同じ。
業界をくまなく見て回っているわけでもないけれど、今仕事をしている制作会社のランクでこのくらいのスタッフということから全体を推察するに、むしろ悪くない、という程度に落ち着いている様に思う。
長い間、クオリティーの高い現場で働いていた人から見れば、多くの現場はいつでもレベルが低いだろうし、レベルの低い現場しかし知らない人にとっては、やはり現場は常にレベルが低い。
私は、あまり作画が凄くいいという現場は知らないが、それでも標準より上は見ていると思うし下もまたそれなりには知っているとい平均的なレベルのスタッフとして30年ほど働いてきたという自覚があるが、その感覚からすれば平均レベルはあまり変わらない、むしろ良くなっているのではないかと思う。
1話数の中にも凄く上手い人とすごく下手な人というのは常にいて(下手にはいろんな理由があるが、とりあえず置いておく)その感覚が上の方に傾いて差異が小さい(つまり上手い人がいて下手な人が、それほど下手ではない)ほどスタッフのレベルは高いと言えるのだが、今やっている仕事は私の感覚的には中の上くらいというレベルなので制作会社の規模を考えるとかなり健闘していると言える。
この制作会社で、このスタッフが集まるのなら業界全体のレベルは満更でもない。
これ以上、作品のクオリティやスタッフの待遇を改善していくためには、制作の効率化などの人的な問題以外の問題を潰していくしかない。
20年ほど前のデジタル環境の導入は大きなトレンドだったが、道半ばで止まり、技術的な制作環境の変革は遅々としている。
もう既にある技術でも色々な可能性があるが、日銭を稼ぐのに精一杯で新しい試みにのり出せているスタジオはわずかだ。
日銭を稼ぐのに汲々としているスタッフとそれなりの収入があっても新しい技術に前向きではない人たちが変革の足を引っ張っている。
業界で出資をしあって作画ソフトを開発するだけでも、大きく生産性は上がる可能性はある。
しかしその様なことが起こる可能性はかなり低い。
AIはもっと個人レベルで、そのような制作環境を大きく変えられる可能性があるので私はかなり期待している。
来年以降になれば映像でも仕事に使えるレベルのAIが出てきそうだ。
今もあるのかもしれないが、権利や倫理などの問題が大きく横たわっているので簡単に出せないという事は考えられる。
私はフルデジタルで仕事をする様になって10年ほどになるが、デジタル環境になってもかなり非効率な作業の仕方を強いられていると思っている。
デジタル環境の可能性の半分も享受できていないのではないか。
もっと制作効率が上がれば個人の時間も増え、より良い作品作りに資するだろうと思う。
タグ: AI
楽しそうなAI【2024年03月24日】
AI面白そう、などと言っているとSNSでは吊し上げに合いそうだが、やはり面白そうである。
画像、動画の分野だとまだやれることは大分限られている印象だけど、実験的にAIを使った映像を見ていると現状でも工夫すればかなり面白そうなことが出来そうだと思う。
かなりワクワクする。
数年後にはAI抜きの制作は考えられなくなるんじゃないかと言う印象がある。
このまま色々AIが進歩したところで何でもかんでも出来る様にはならないので、基本は人間との共同作業だろう。
使い方次第で色々なことができる様になりそうだ。
AIを使った映像を見ていると、今まで以上に映像のアニメーション化が進む様に思う。
現状、動画生成系のAIに求められているのはフォトリアルな映像を作れる様になるということの様だ。
この方向で進化したとしてもアニメーション化していく。
アニメーションとは何かと言う定義はどんどん拡張していて、CG映像をアニメーションとした時からフォトリアルな映像は、とうの昔からアニメーションのカテゴリーの中に内包されてしまっている。
ライブアクションとアニメーションの違いは、現実の『時間』を映しているか、そうではないか位の大雑把なカテゴライズになってしまった。
現状のAIの映像を見ていると人の手が入っているのは明らかで、それは非常にアニメーション的だ。
特にCGを使った映像に似ているものが多い。
そう遠くない未来に現実と見まごう映像が可能になることは間違いない、というかCGにだって現在それが可能だしフェイクのようなAIを使った映像も既にある。
ライブアクションとそれら映像の違いが見分けることが、やり方によっては非常に難しくなる。
しかし、概ねの作り手が求めるのは、そう言うものではなく、フォトリアルであってもアニメーション的なものになると思う。
そうなって手描きのアニメーションは何をやるのかな?ということについて考えるのは面白そうだ。
AIを使えば手描きの様な手描きではないアニメーションも可能になるので、人間の役割も作品によっては大きく変わっていくだろう。
アニメーションを作るのには何と言ってもとてつもない時間がかかっていたのがもっとお手軽な表現として作れる様になるかもしれない。
結局アイデアが一番重要ということになる。