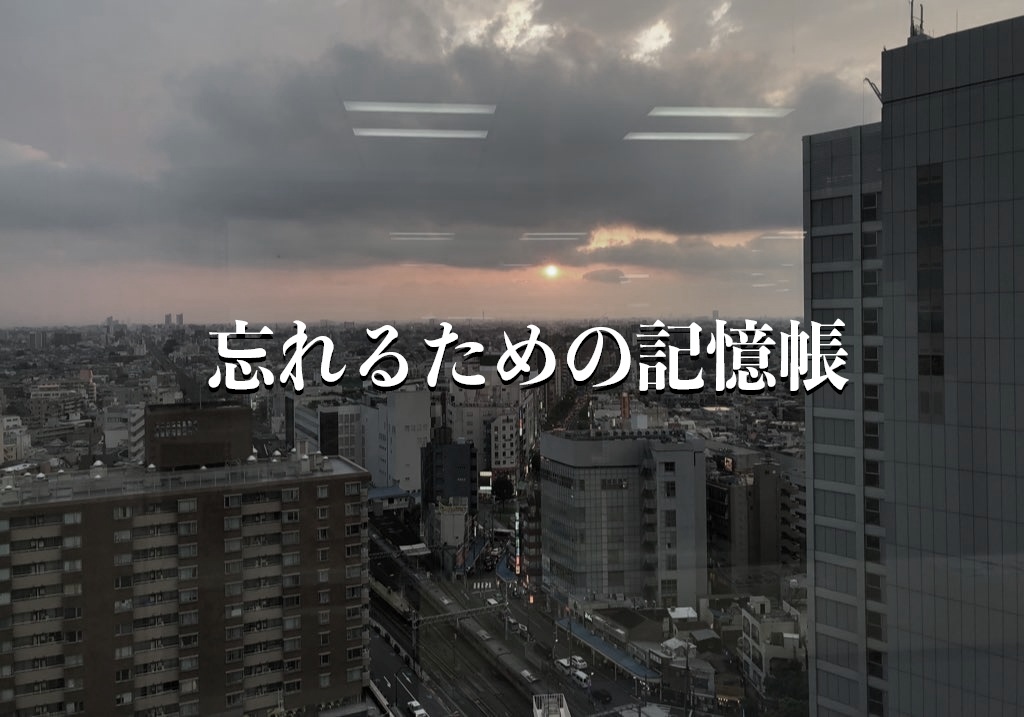1日だけ水をあげられなかったキク科の植物がカラカラに干からびていて、これはやっちまったなと思いながら祈る気持ちで水を与えたら、昼にはしっかり復活していてホッと胸を撫で下ろした。
暑さ寒さに強いという種類ではあったものの、しょぼしょぼに縮んで鉢に這う様にしなだれていた葉があっという間に復活したのは驚く。
流石に新芽などは痛んでいて、本格的に復活するには時間がかかりそうだけど。
どうもここのところ沢山枯らしてしまったので、諦めていたのだが強い種類は本当に強い。
特にキク科の花は強いものが多い印象で、結構いろんな種類を買い込んだ。
エキナセアもキク科。
菊と言えば和風のお供えに使うようなもののイメージしかなかったが、園芸種は色んなものがあって本当に楽しい。
ローダンセマム、オステオスペルマム、エキナセア、アスター、etc
たぶんキク科の植物が一番多く生き残っている。
暑さに強くても葉焼けして葉の一部が干からびてしまっているものも多い。
これはどうにも避け難いような気はするが、何かいい方法があれば知りたい。
少しだけ時間ができそうなので、映画理論系の本を読み始めた。
古い本なのだが、基本は今も変わらなく参考になる。
しかし、改めて理論系の本は難しすぎるところへ突っ込んでいってる感がある。
物語表現の技法を簡素に教えるようなものはないのかも。
シド・フィールドの脚本の書き方を教える有名な本も1冊読んだ。
何冊かあるのだが、大体内容は察した。
具体的な脚本の作り方ではあるのだが、いきなりハリウッド映画のようなものを書きたい脚本家の卵を向けた本なので、初心者が読んでもかえって分かりずらい。
しかも何か書きたいことがある人、を想定していて、そんな人は殆どいないだろう…と私は思う。
書きたいものとかなくても、そもそも人間は物語形式で何かを理解したり伝えたりするので、もっと素朴な教え方が可能なのではないだろうか。
実際仕事にしてしまったら、シド・フィールドの本のように見せ方について考えたりもせざるを得ないと思うが、初めからそれを教えても混乱を招く。
どこかの若い演出家が現場で使える辞書的な演出の本をクラファンを募って出そうとしているようだ。
なるほど、確かにそいう本はないのだが、どこまで本で伝えられるものなのだろうか。
私のやろうとしていることも似たような事ではあるのだが、細かな用語などは現場によっても違うし、あまりディティールに突っ込むのは難しいと思っている。
最近はオン・ザ・ジョブ・トレーニング、OJTで教えてもらえる機会も減っていると思うので、そいった本の需要が有りそうだという事なんだろうが。
結局最後は、表現の技術なんかよりもっと面倒で難しいことが演出家を待ち受けている。
それこそ「何を」描くかなのだが、原作もの全盛の中、そんなことを考えることもアニメの演出家には求められていないようにも見える。
しかし、そこから目をそらすのも不可能だ。