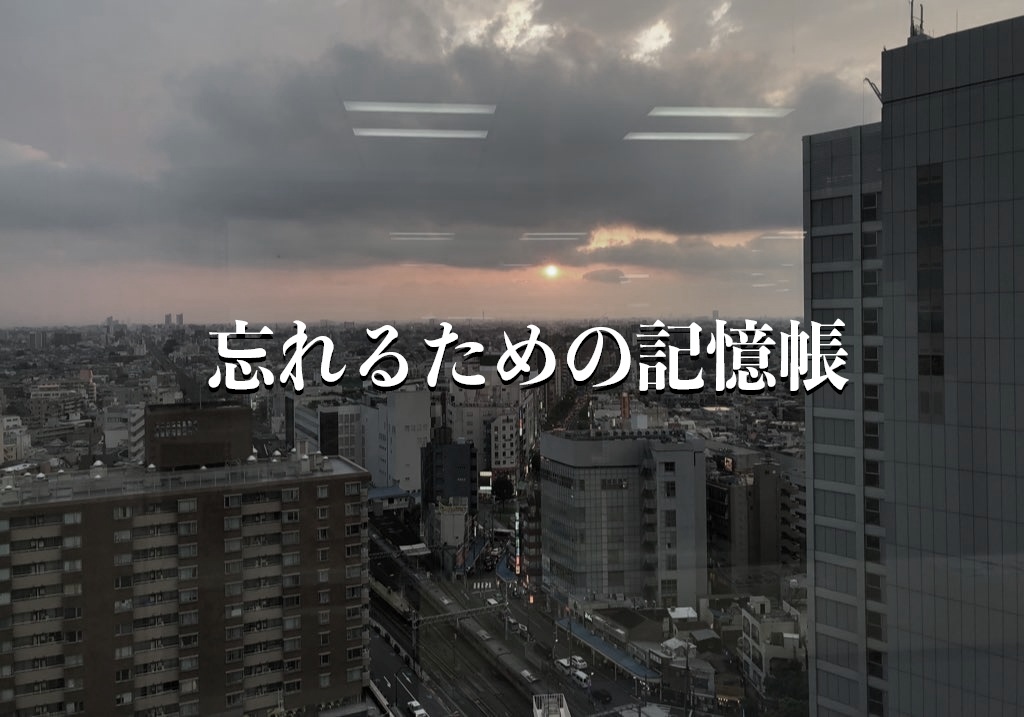もう9月も残り2日。
今週はちまちま仕事とJAniCAの理事会があったり。
そういえば、いま「マンガ、アニメ、特撮、ゲーム等の国際的な振興拠点及びメディア芸術連携基盤等整備推進に関する検討会議」というのをやっている。申し込めば会議の様子をYouTubeを通じて動画で見られる。
博物館的なものを作ろうという計画があってその会議。
石破茂が自民党の総裁に決まったが、石破さんはオタクなので、もしかしたら本当に箱物が出来るのかもしれない。
緊縮であっさり無くなる可能性もあると思うが、実際できたとして他の分野はともかくアニメ・特撮は報いることができるのだろうか。
アニメは一応外貨を稼げそうな雰囲気はあるけれど、ほとんどの現場には今だに余裕のある予算は無いので疲弊して倒れるのとどっちが先かのチキンレースだ。
あ、週の頭はOTOの周年に行ったのだった。お祭り感があって久しぶりに楽しかった。
今日は木ノ下歌舞伎「三人吉三廓初買(さんにんきちさ くるわのはつがい)」を観劇。
間に休憩が25分、20分とあるけれど三幕5時間20分ほどの長丁場。
面白かったので、あっという間ではあったけれど、さすがに膝が少し痛い。
木ノ下歌舞伎は歌舞伎を現代語訳&現代的演出で見せるので素人でもとっつきやすい。
歌舞伎通の客も結構いるのだろうが。
最後はスタンディングオベーション、カーテンコール4回もやってくれたらそりゃ皆んな立つよね。
筋立ては、親の因果が子に報い、あらゆる登場人物が縁を結んでいることが徐々にわかり、それぞれ破滅を迎えていく。濃厚な親子の関係がモチーフになっていて重たいが重すぎて現実味がないというようにも思える話。
若い頃だったら嘘くさい様な気もしていたかもしれないが、今見るとシリアスでゾッとする。
家族というのは病の温床だが、さりとておかげで生きていけることもあるという厄介なものだという様なことをとある精神科医が話していたのを思い出したりもした。
鹿島茂は小説は結局、家族の話だけだというようなことを言っていた。
科学の発展で自然からはある程度距離を置いて生きることができる様になったものの、人間同士が距離を置くのは容易ではないよなー。
しかし、そんな重い話を外連味たっぷりに見せているからこそ、今でも人気の戯曲なのだろう。
ラストにかかる挿入歌はTaku Takahasi、ラップのリリックをロロの板橋駿谷がやっているのも面白い。
大脇幸志郎「なぜEBMは神格化されたのか・誰も教えなかったエビデンスに基づく医学の歴史」が面白そう。
本の紹介によると
エビデンスに基づく医学(EBM)という言葉が、あたかも医学が事実の裏付けのない空理空論からすでに脱却したかのような含みで語り交わされている。しかし、実際には医学における重要な判断にエビデンスが必須どころか努力目標としてすら求められていないという事実がある。
本書は、公衆衛生の発達、臨床医学の飽和、薬害事件による臨床試験の制度化などを背景として医学が統計技術を取り込んだ歴史や、EBMという言葉を考案した人物たちの来歴を紹介する。さらに、エビデンスについての誤解や拡大解釈から発展していくイメージとの相互作用に注目することで、医学が生産的に実証性を維持するための課題を探る。巻末に索引、用語解説、年表、主な登場人物一覧、医学雑誌歴代編集長一覧などを付する。
ということらしい。
エビデンス…と言われると弱いね。
大脇氏とシラスで対談していた松本俊彦氏の本も読んでみたいのだが…。
積読をもう少し解消してからか。
今週の積読消化。
だいぶ前に買っていた渡辺大輔「明るい映画、暗い映画」、藤山直樹「集中講義・精神分析(下)」
渡邊大輔氏の本は結構面白かった。
しかし、前半の批評は映画のための批評という感じで外側にあまり開かれていく感じがしなくて、そこは苦手。
後半の普通の映画評の方が面白い。
とくに鬼滅の刃については全く同意。
藤山直樹氏の方はフロイト以後の精神分析の歴史。本当にざっとさらっていく感じなので、興味のあるところは参考文献に上がっている本を読まないとよく分からない。
精神分析は実践がないと本を読んだだけでは何も分からない、と藤山直樹は言っているが。
精神分析には暇とお金がかかるので、無理じゃん?
精神医療は最近やっと少し理解できた気がするが、結構勉強しないとよく分からないし、イメージが掴みずらい。
いま?NHKで統合失調症に関するドラマがやっているけれど、精神科や心療内科は、外科・内科みたいなわかりやすさや親しみがない。
子供の頃から通い慣れてれば何となくイメージもつくのだが、そんなことはないので。
情報は探せば結構あるのだが、パッと感覚的に鷲掴みにすることは難しいし、1冊2冊、本を読んでも分からない気がする。なんとかならんもんか?