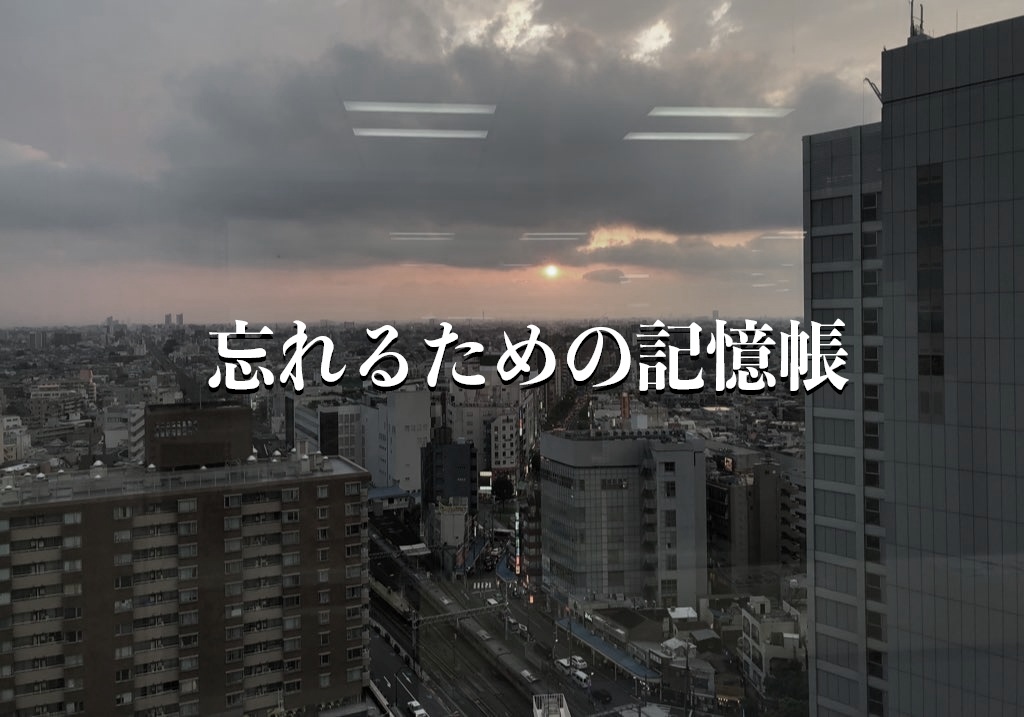順番に内容を整理
GPTの整理では、
1. ストーリーボードの基本的な目的を理解する
- 目的の説明: ストーリーボードは、映像のシーン構成やカメラワーク、キャラクターの動きを視覚的に整理するためのツール。シナリオから映像化の第一歩であり、アニメーターや制作スタッフとの共通言語となるものだと説明します。
- 具体例の紹介: 完成したアニメーション作品のストーリーボードと映像を比較しながら、どのようにストーリーボードが映像に変わるかを実例で見せます。
アニメーションというか我々が作っている商業アニメーション(この様式に対する明確なネーミングはないのは問題だ)を制作する上でストーリーボードがどの様な役割を担っているのか整理する
- 実際に制作する映像を視覚的にわかる様に計画する
- 物語全体の時間の想定または算出。全体の時間をどの様に分割するか、しないかを計画する。
分割単位は大きくシーンとカットがあるが、シーンはシナリオで既に想定されているので、基本的にはカットの単位で分割を考える - 映像内で起こる事象の提示(場所、演技、その他主要な映像に写すことが必要な事象)
- 事象をどの様に映し出すかの提示(フレーミング、カメラワークの提案)
- 部分、全体の作業負荷の想定、見通しを立てる
- 音響についても大まかに想定する場合がある
演技をストーリーボードで想定するのは、日本のアニメの多きな特徴。
実写だったら俳優の演技があるので、演出家が事前に想定する部分は限定的だ。
日本のアニメは作業負荷の想定やキャラクターの統一などの理由から、かなり踏み込んだ部分まで演技が描かれる場合がある。
作業者の負担になる部分でもあり、面白いところでもある。
大まかな項目としたらこんなところか?
ストーリーボード作成の目的自体は初心者にも比較的容易に理解可能だろう。
ただ実際のストーリーボードは、作品や監督などによって「どこまで踏み込んで考えるか」や「重要な要素」が大きく違う。
しかし演技、撮影効果、音響など、何をどこまで想定するのがストーリーボードの役割なのか、初心者にはある程度明確にしておくべきだろう。
あくまで商業アニメ制作に絞って、その役割をもう少し整理してみる
・時間の算出
演出家を仕事としている身としては、このことが非常に重要だ。
何故なら、尺が足らなくてもオーバーでも商品としては成立しない。
映画であれば厳密なフォーマットは存在しないものの、90分と120分では、製作費が変わってくるし上映可能回数も変わってくる訳で、適切な尺に収めるのは管理職としての演出家に常に求められる。
しかし、超初心者に教える場合や、演出の概念やストーリーボードの仕組みを教えるだけであれば、あまり教える必要はない。
実際、学生の時はこんなことを言われたことはなかった。
プロになってからは、尺が上手くコントロールできなくて冷や汗をかいたことが何度となくあるのだが…。
とりあえず各項目ごとに、これは初心者に必要か?ということを整理していくしか無いかも。
・演技の想定
これは結構、初心者でなくても難しい項目。
初心者にストーリーボードを教える場合、実は「演技については考えさせない」方がストーリーボードの仕組みはわかりやすいかもしれない。
映像のつながりを想定するだけであれば詳細な演技は必要ない。
ただ画面内のキャラクター(人物)の位置が想定されていれば良いだけである。
実写の様にカメラが移動して構図が変わる場合でも、見かけ上のキャラクターの位置が分かれば繋がるかどうかは判断がつく。
キャラクターが移動する場合でも、同じく画面内の見かけ上のキャラクターの位置が分かれば良い。
芝居を一緒に考えると混乱したり、映像の繋がりについて忘れたりしがちだ。
しかし実際のアニメの現場では、演技の想定が演出家というかストーリーボードを描く人間に強く求められている。
理由としては、
・全体の作業量の想定
・キャラクターの統一
・アニメーターが演技を考えてくれない、あるいはその時間がない
などがある。
これは初心者がストーリーボードを学ぶ際に結構足かかせになっている気がする。
初心者に教える場合は、ストーリーボードで求められる演技について整理しておく必要があるやに思う。
抽象的にも具体的にもなりすぎない様に、ストーリーボード作成の目的を整理しなくてはいけない。
そしてそもそも、誰に教えると想定するのかハッキリさせる必要がある……のだが、超初心、初心、中級者でだいぶ内容が変わってしまう。
今回はここまで。