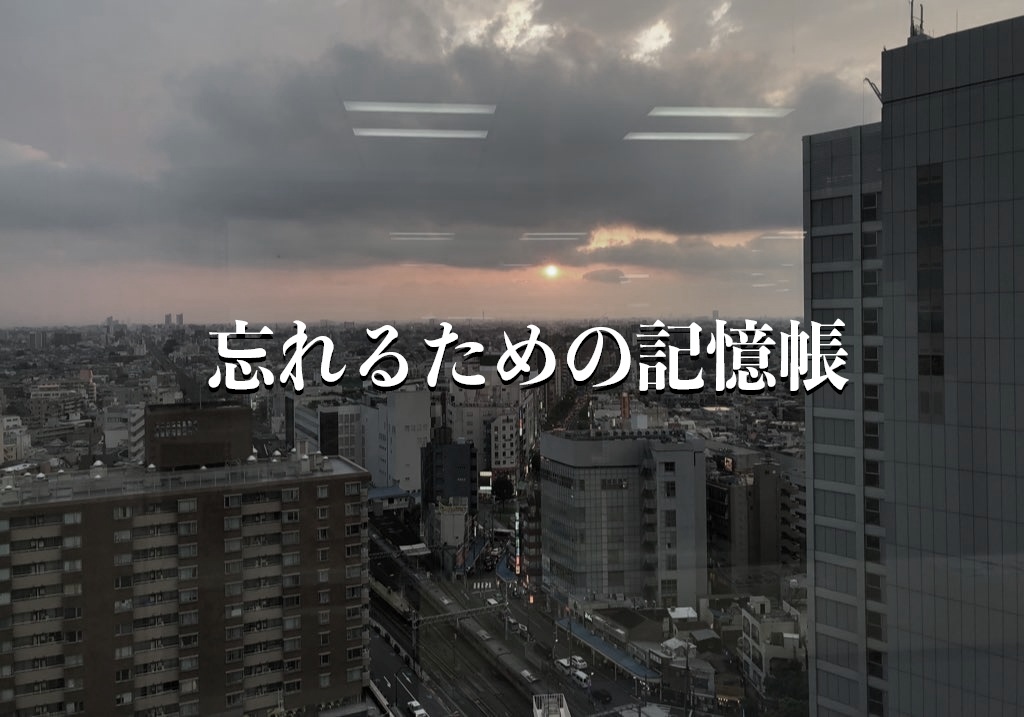数日、昼間の気温の高い日が続いた時、うっかりバーベナとオステオスペルマムの水やりを忘れていて気づいたらバーベナが葉っぱがくしゃくしゃに萎んで瀕死状態になっていた。
白に紫の斑が入った美しい花が咲いて気に入っていたのだが、これは枯れたなと凹みつつダメ元でバラしてスリット鉢に入れて養生を試みた。
寄せ植えをバラす際に根っこもかなり切ってしまって、ちょっと回復は難しいだろうと思っていたのだが、水をやって半日も置いておくと葉は完全復活。
驚くほど強健で歓喜した。
結構長いこと寄せ植えで置いてあったので、あまり株は大きくなっていないが、この調子なら結構大きくなってくれそう。
オステオも根は切れてしまったものの葉が元気だったので問題なく回復しそう。
他にも水切れが激しいヘリオプシスとヘリアンサスを6号鉢に植え替え。
両方とも根がビッチリと伸びていて、春に目が出たばかりの苗とは思えない位に成長していた。
鉢増ししたエンジェルウィングも問題なさそう。
雨で調子を崩していたスカビオサは結局お亡くなりになった。
残っていた地植えのビオラは抜いてあまりにも株が大きくなっているので実験として花を落として日陰で養生してみている。
基本暑さに弱いので、これから本格的に暑くなったら耐えられないとは思うのだが。
ヒヤシンス、アネモネの球根も掘り上げた。保存方法を検討中。
バーミキュライトに埋めておくのが良さそうだが、容器の通気性の確保が必要。
ビオラがあったスペースに、白いベロニカと明るい緑のヒューケラを植えた。
モッコウバラの下なので日当たりが良くないが、果たして。
昨日は雨が強そうとの予報だったので、鉢は軒下へ。
風は思ったほど強くなかったが、ジギタリスは倒れそうになっていたので支柱で支える。
まだ植え替えていない植物が結構残っているが、週末雨が多いのであまり進まないかもしれない。
予報通り土曜は雨。
ウドンコで弱っていたガイラルディアは復活してきた様だ。
薬をかけすぎていたのか葉が紫に変色していたのは薬害が出ていたのかもしれない。
今朝はだいぶ緑に戻っていて水は切れているが調子は良さそう。
晴れたら水をあげよう。
ジークアクスを最新話までゆるっと見た。
ニュータイプは新人類のことを指していると思っていたが、新人類が流行ったのは80年台だからガンダムの方が先だ。
劇中の意味合い的には新人類と同じ様なニュアンスと思えるので、富野さんのセンスが良かったのだろう。
初代はハッキリと当時の若者を描くことを意識していたと思われるけど、今はその対象となる若者像が判然としないからなのか、何を描くのかぼんやりとしている様に見える。
初代はソフトな戦記物として、うまく機能していた様に思う。
第二次大戦が終わってから80年ほど、戦争そのもののイメージが変わっている。
ガンダムが戦記物というスタイルを捨てないならば、それとどう関わっていくかは重要になってしまう。
ジークアクスは戦記物としては、ふんわりとした立場をとっている様に見える。
モビルスーツ同士のバトルゲームを軸に据えることでライトにとっつき易くしようということかもしれない。
私は戦記物には全く疎いし積極的に見たり読んだりするわけでもないが、自分でやるならどストレートな戦記物が好み。「鷲は舞い降りた」のようなキャラクターが好感の話とか。
モビルスーツのモチーフは鎧なのだし、ザクのような一つ目は鬼・幽霊などを想起させるので平家物語の様な日本の古代の戦記物を翻案するのも面白い様に思う。
平家物語は高畑勲がずっとやりたがっていたが、宮崎駿は鎧を描く大変さをわかっていないと退けていと聞く。確かに現実の鎧は大変だがモビルスーツの様な抽象化されたキャラクターを使えば可能かもなと、思ったりもするが3Dを使えば現代なら人間のキャラクターでも表現可能だから、モビルスーツでやる意味は薄いか…。
ヒット作を作るには何らか現代との繋がりを作らねばならないと思うが、うまく繋がりを作れるかどうかは腕が問われるし、偶然性みたいなものも関わってくる。
たまたま、より深くつながれた作品はヒットする確率が高い。
ヒットなんて狙わなくてもよければ現代性なんて気にする必要はないのだが、商売で作っているものは無縁ではなかなか居られない。
現代とどう切り結ぶかがポップカルチャーの面白いところだと思えば、向き合うしかない。
昨日の名人戦は逆転で藤井聡太が勝ち。
この人を終盤で振り切るのは容易ではない。
今週はアフレコが少しトラブルがあってやり切れず。
あとは自分の手持ちのコンテを終わらせてしまえば随分と楽になる。
肩が上がらなかったりしたので、今週はゆるゆる進行。
おかげで少し楽になってきた。
6月後半は少し遊びの予定もあるので、早く片付けなければいけない。