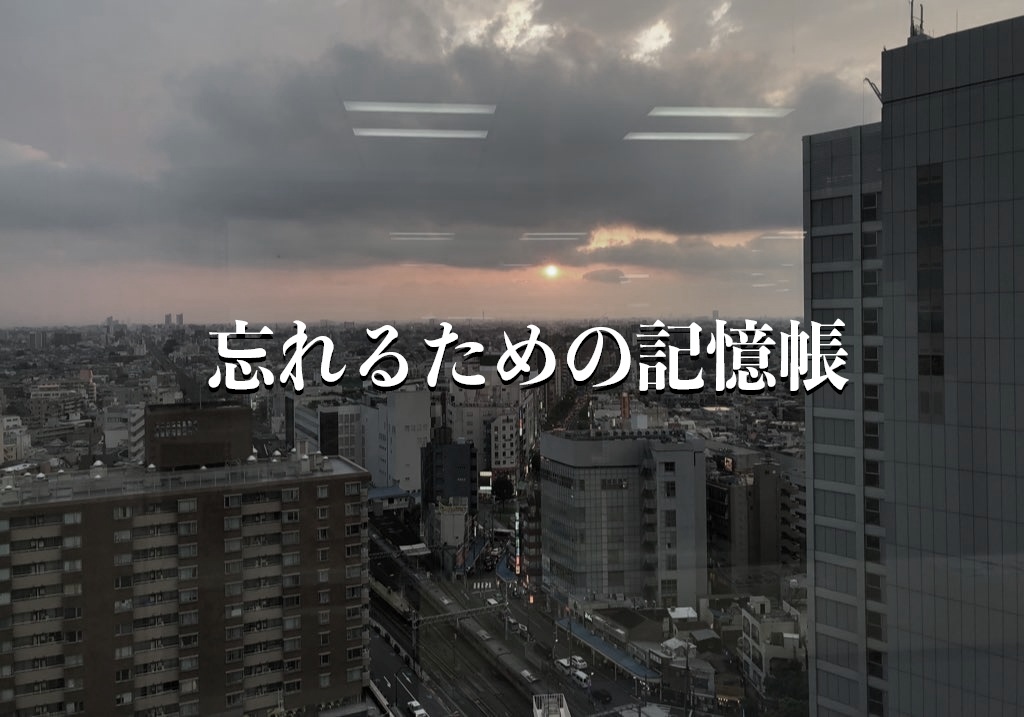たまーに若い子に絵コンテを教える機会もあり、なかなかオーソドックスな絵コンテのスタイルや描き方は教えられていないのだなと思うことがしばしばあった。
なので、絵コンテに興味がある人向けに教育的メソッドを作ってみようと思い、しかし一から作るの手が掛かるのでどうしたものかと思っていたが、電車の中で半分暇つぶしに、絵コンテ制作を新人演出に教えるアイデアを提案せよとChatGPTに投げてみたところ、意外とまともなアイデアが返ってきて大変驚いた、と共にこれを叩き台にして作れば、あまり時間をかけずに出来るかもしれないと思ったので早速始めてみることとする。
以下はchatGPTの提案である。
ChatGPT
新人の演出家にストーリーボードの描き方を教える場合、基本的な技術から応用まで段階的に教えることが効果的です。以下の順番で教えると、理解が深まりやすいです。
1. ストーリーボードの基本的な目的を理解する
- 目的の説明: ストーリーボードは、シナリオを視覚的に整理し、映像の流れを決定するツールであることを説明します。キャラクターの動きやカメラの視点、シーンの構図などを計画し、チーム全体に作品のビジョンを共有するために使われることを強調します。
2. シナリオの分解と解釈
- シナリオの分析方法: まず、シナリオをシーンごとに分け、必要な演出要素(アクション、対話、感情表現など)を把握する方法を教えます。
- 重要シーンの特定: ストーリー全体の中で特に重要なシーンやクライマックスを特定し、その部分を重点的に描く技術を学ばせます。
3. カメラワークの基本
- 視点とアングルの基礎: 視点(主観/客観)やカメラのアングル(高い視点、低い視点、横からなど)の違いが映像に与える効果を説明します。
- カメラの動き: パンやズーム、トラックなどのカメラの動きをストーリーボードでどう表現するか、動きに合わせてシーンをどう切り替えるかを教えます。
4. 構図とレイアウトの基礎
- 三分割法や視線誘導: 三分割法などの基本的な構図のルールや、観客の視線をどこに誘導するかを学びます。
- 空間の使い方: キャラクターやオブジェクトの配置が、シーンの緊張感や動きにどのような影響を与えるかを説明します。
5. キャラクターの動きと表情の描写
- アクションの分解: キャラクターの動き(歩く、話す、戦うなど)をどのようにコマ割りで描くか、動きの流れやスムーズさを意識したストーリーボードの作り方を教えます。
- 表情の変化: キャラクターの感情を伝えるための表情の変化をどのように描き、シーンに反映させるかも重要です。
6. シーン間の繋がりとテンポ
- シーンの切り替えと繋がり: シーンのスムーズな切り替えや、ショット間のテンポの取り方を説明します。カット間のリズムやテンポ感が、視覚的な効果や感情の高まりをどう変えるかを学ばせます。
- テンポとリズムの重要性: アクションシーンと静かなシーンの対比や、リズムを意識した編集の仕方を教えます。
7. 効果的な映像言語の使い方
- 象徴やメタファーの導入: ビジュアルに意味を持たせる方法や、観客に暗示的に伝える演出手法を紹介します。たとえば、特定の色や形がシーンにどのように意味を加えるかを学びます。
- サブテキストの表現: キャラクターが話している内容以外の、裏の感情や状況を視覚的にどう表現するかを教えます。
8. ライティングと影の活用
- 照明効果の理解: 光の当たり方や影の使い方が、キャラクターやシーンの感情にどのような影響を与えるかを説明します。
- 時間帯や天候の表現: ストーリーボードで時間の流れや天候の変化をどのように描写するかを学ばせます。
9. 音響と音楽の考慮
- サウンドキューの入れ方: ストーリーボードには音響や音楽の指示も含める場合が多いため、どのタイミングで音が入るか、シーンに合わせた音響演出の指示を追加する技術も教えます。
10. フィードバックの重要性
- フィードバックを受け入れる姿勢: ストーリーボードはチームで共有するものであり、他者からのフィードバックを受けることが重要です。建設的な意見をどのように反映させ、より良いストーリーボードにするかを教えます。
教える順番のまとめ
- 目的の理解
- シナリオの解釈とシーンの分解
- カメラワークの基本
- 構図とレイアウト
- キャラクターの動きと表情
- シーンの繋がりとテンポ
- 映像言語の使い方
- ライティングと影の活用
- 音響や音楽の考慮
- フィードバックの受け入れ方
新人には、まず基本的な要素を学ばせ、徐々に複雑な技術やクリエイティブな要素に移ることで、全体的な理解を深められるようにすると良いです。
とのことだった。
かなりそれっぽい。
イマジナリーラインについて触れられていなかったので、
あなた:イマジナリーラインについて教える場合、上記の項目の中の何処に追加するのが良いですか?
と質問すると以下の答え。
ChatGPT:
「イマジナリーライン(180度ルール)」は、カメラワークの基本やシーン間の繋がりとテンポに密接に関連しているため、これらの項目の間に追加するのが良いです。
具体的には、以下の位置に追加することを提案します:
3.5. イマジナリーラインの理解
- 180度ルールの説明: イマジナリーラインとは、シーンにおけるキャラクターやオブジェクトの位置関係を保つために、仮想的に引かれる線のことです。カメラがこのラインを越えて位置を変えると、観客がキャラクターの位置関係や動きを混乱する可能性があるため、基本的にはラインを超えないようにします。
- シーンの連続性: イマジナリーラインを守ることで、視覚的な連続性が保たれ、観客が自然にシーンを理解できることを教えます。
- ルールの活用と破り方: ルールを意図的に破って感情の変化や混乱を演出する方法もあるため、その使いどころについても説明します。
このように、カメラワークの基本に関連した要素として教えるのが最も自然で効果的です。カメラアングルや視点と密接に結びついているため、このタイミングでイマジナリーラインの概念を導入すると、より理解が深まります。
なるほど…と感心。
これをさらに詳細にしたアイデア出しもしてもらったのだが、一般的に教えていそうな項目を多数並べてくれた。
が、詳細になるほど抽象的になっている印象。
しかし、根本的なことには何も触れられないまま、理屈めいた映画の理論が教えられていることは今も普通に起こっていそうな気がする。
そもそもの話ではあるのだけれど、映像文法は数学のようなものではない。
音楽のメソッドなどに近い。
短調は長調に比べると暗く聞こえる、と言われているが、それは数学の法則のように理由が説明されているわけではない。(認知心理みたいなもので説明を試みられてはいるのかもしれないが)
ポップスのコード理論なんかも、こういうフワッとした経験知的なものをベースに作られていると思うのだが、映像文法も似たようなものだと思う。
ほとんどの事は経験的な感覚を下敷きにして作られているので、時代によって変わることもあるだろう。
歴史、積み上げてきたものが大事なのだ。
理論は割とフワッとしたまま、感覚だけで作品を作っている演出家も少なくはないと思う。
私も大学で多少教育は受けたもののかなりフワッとしたまま、言語化しないまま仕事をしている部分も多い。
しかし、経験に頼りすぎるのは若い人が演出を学ぶ時、人によってはえらく時間がかかってしまう原因になりやすいように思うし、全く出来ないまま終わるということにもなりかねない。
映像文法は今まで人間が「映像から物語を理解する」にはどうしたら良いかという経験知の集積なので、そういう意味で有用だと思う。
私は映像文法の基本部分は極めて簡単だと思っていて、骨格だけ覚えたら、あとは経験値で膨らませ応用を考えていく他にないように考えている。
GPTが挙げていることは重要だが、「物語を映像で表現する」ための方法という映像全般の技術の中の限定的な分野の事でしかないので、全部を理解している必要はないし重要度も項目によってかなり違う。
4の構図とレイアウトについてなどは私の場合はかなりいい加減に考えている。
色々整理しながら、初学者が分かりやすいようにと、形式主義に陥らないように演出の基本をストーリーボード(絵コンテ)作りから学べるような方法を考えてみようと思う。
まずははここまで。