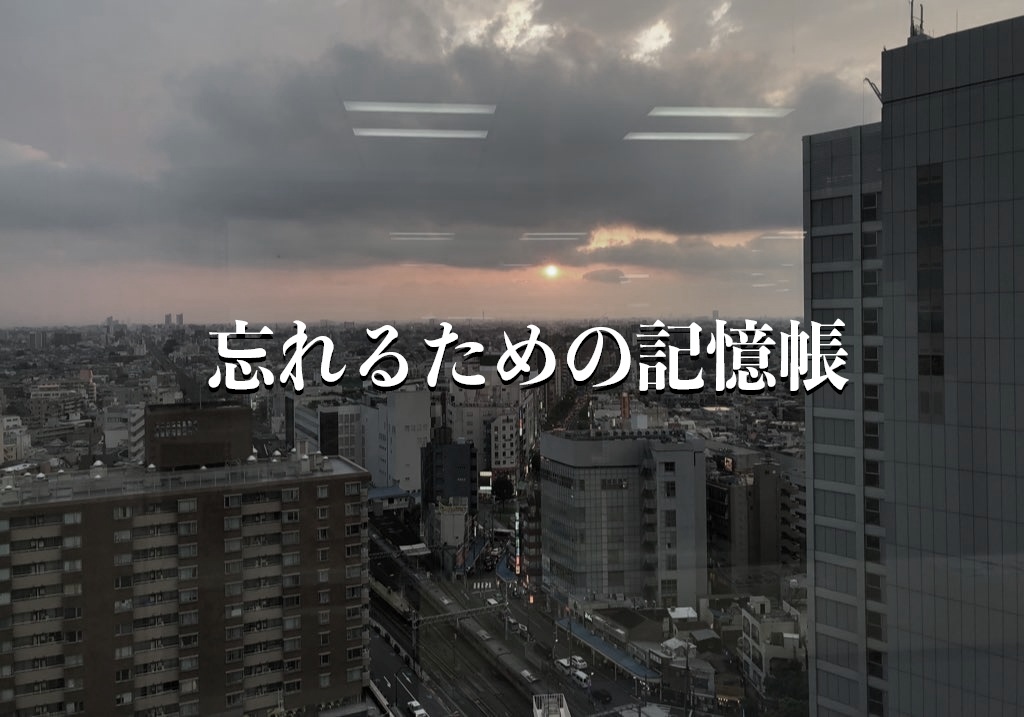制作中のアニメのアフレコが終わったりで少しほっとした週末。
多少、打ち上げっぽいことも出来るようになった昨今、役者さんとも少し話ができて楽しく過ごした。
土曜はロロの「飽きてから」を内古閑さんと観劇。
いきなり別れ話から始まるようなところが、今までの三浦さんとは少し違う感じ。
食事についての会話がいきなり別れ話に接続してしまうのは面白くもあり、とてつもなくリアルな感じもして、胸がギュッとする。
時制の繋ぎ方の面白さは相変わらずでどうしてこんなことを思いつけるのかと毎度思う。
短歌をシーンの間ごとに挟むという趣向は、考える間隙が生まれるようでなかなか良かった。
鈴木ジェロニモが歌う「瞳を閉じて」も最高だった、劇中では涙を誘うまでに至らず失敗という設定なのだが笑えながらもしみじみと響く。
ジェロニモ?何でそんな名前?と思って調べたら芸人さんらしい。
Rー1で準決勝まで行ったというwiki情報を知る。
短歌が趣味らしく、それもあってのキャスティングなのだろう。
終演後、側にいた客の会話が聞こえてきて、結構有名な歌人も見にきていたことを知る。
移動のタクシーの運ちゃんが自民との総裁は誰が良いと思うかなどと問うてきた。タクシーで政治の話などしていると危ないんじゃないかと思うが余計なお世話か。大谷翔平の話も振られたが、前日たまたまテレビでニュースを見ていたので会話になった。
ソニーが開発しているというアニメ制作用のソフトは仕上げ機能も組み込んであって、どうもガチで使えるものになりそうだ。
朝日新聞の記事によると仕上げ機能から現場投入されるようで、RETASの保守が効かない事への危機感から開発されたことが窺える。
もう10年以上前にRETASの開発は打ち切られているのだが、放置され続けてきてアニメ業界の不甲斐なさを思い知らされていたが、ここにきてやっとRETASの代替になりそうなソフトが出来そうだ。
他にも仕上げのできるソフトはあるのだが、RETASとは思想が違って、同じような素材を作るための使いやすさがだいぶん違った。
RETASの素材に業界全体は特化しすぎてしまっているのもどうかとは思うが、共通フォーマットがあるからこそ現在のような物量でアニメが作れていることは間違いない。
後継ソフトは悲願というと大袈裟だが無くては立ち行かないだろう。
庭の木を切った枝にコガネムシが付いていた。
コガネムシの幼虫は花木の根を食い荒らすので害虫とされているのだが、ゴミ袋に突っ込むのも忍びないので、そっと地面に置いた。